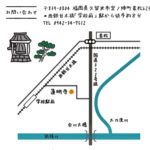お寺のこと

蓮明寺は、仏様の摂取不捨「えらばず・きらわず・みすてず」の心、「愚者」として真実に生きようとした親鸞聖人の歩みを大切にしています。
亡き人をご縁とした仏事を勤め、法要を営み、だれもが参加していただける行事や教室を通して寺を開き、やさしいご縁をつなぐこと、悲しみや迷いの中で生きる力を育むことを、寺の使命としています。
人生の悲喜交交を仏法にたずね、御念仏の御法を分かち合っていきたいと願っています。
【本尊】阿弥陀如来
【宗祖】親鸞聖人
【宗旨】浄土真宗
【本山】東本願寺(京都)
【宗派】真宗大谷派
歴史
有馬藩の記録「寛文十年久留米藩寺院開基」によると、蓮明寺開元は永正3年(1506年)、元祖善保の建立とされています。大正頃に書かれた沿革には、薩摩の浪士、溝邊兼三定房が御井郡大堰村菅野に住し、その子溝邊聞三定明が祖先の菩提を弔うために剃髪し善甫と名告り、寛永元年(1624年)御井郡恋之段村に寺院を建立したと記されています。1506年に善保によって開元された蓮明寺を、1624年に善甫が再興したと考えられます。
【溝邊兼三ー溝邊聞三(善甫)】
薩摩の浪士、溝邊兼三という名は、安土桃山時代に加治木・溝邊領を治めた肝付兼三(1585-1602)の流れを汲むと推測されます。肝付兼三の父である伊集院忠棟が本願寺に帰依した念仏者であったこともあり、一族は本願寺と深いつながりを持っていました。兼三は1599年に喜入肝付家を出奔しており、藩外に逃れ浪士となっていたと思われます。伊集院忠棟は朝鮮出兵後の島津忠恒に斬殺され、その後、庄内の乱を起こした伊集院忠真及び一族は1602年に抹殺されました。一族の盛衰を見届けた溝邊聞三(善甫)は、世の無常を想ってこの地に根を下ろし、本願寺の寺を開いていったのでしょう。
山号は「多聞山」。「聞く」ことを願われてきた寺です。「多聞第一」と呼ばれ、釈尊の教えを最期まで聞き続けた阿難尊者が想起されますが、浄土真宗の門徒は、「仏法聴聞」を生活の要としてきました。その伝統を「聞法の道場」として地域で受け継ぎ、地元の人々の心のよりどころとして護持されてきました。
仏事について

人に会い得た事実を深く感じる場として、仏法に遇うご縁として、浄土真宗の仏事は営まれてきました。
御本尊を中心とした丁寧な儀式の執行を通して、ご遺族の伴走者でありたいと思っています。
よくお問い合わせを頂く内容について、以下にQ &Aを作成しました。参考にしてください。
Q 門徒(檀家)ではないけど、仏事はお願いできますか?
A ご依頼をいただければ、門徒(檀家)でなくとも、日時等をご相談の上、真宗大谷派の作法で仏事をお勤めいたします。
Q お布施の額は決まっていますか?
A 決まっていません。「基準がわからない。相場を知りたい」とおっしゃる方には、過去に頂いた例をお伝えします。
Q 布施以外に、お寺と関わることでお金は必要ですか?
A 蓮明寺では、門徒の皆様に一戸1万円の年会費(懇志金)をお願いしています。境内建物の護持や建物保険、本山東本願寺への納金等の費用を分かち合うためです。新納骨堂(2024年完成)に加入する方は、別に護持費年5,000円を頂く予定です。それ以外に、寄付や布施の強制は一切ございません。
Q 赤ちゃんの初参り、子供の七五三、結婚式などは、寺でできますか?
A 人生の節目に仏縁をいただくことは、とても有難いことです。承っています。ただし、土日の日中は法事等の予定が入りやすいので、お早めにご相談ください。
Q 永代供養はできますか?
A 昨今言われる永代供養には、大きく3つの意味があります。
①死後の墓を世話する親族がいないため、故人のお骨を永代供養として納める。
②年忌法事を勤める親族がいないため、故人の年忌を寺が勤める。
③永代経として、永代にわたってお経(仏法)が伝わるよう懇志を行う。
いずれも、ご相談に応じて承っております。
Q 永代供養の費用は?
A お骨を納められる場合は、新納骨堂の永代供養室において、骨壺一口につき10万円で永代にお預かりいたします。その他、読経についての布施の金額に決まりはございません。また、永代経懇志として納金頂ければ、仏具備品の新調・修理、寺院の公益事業のために使用させていただきます。
寺院利用について
Q 仏事で寺を利用できますか?
A 可能です。寺を利用される方は増えています。使用料は、葬儀のみ3万円、通夜葬儀5万円と内規で定めております。その他の仏事・読経の利用料は定めはございません。
Q 仏事以外では?
A 趣旨が公益に適うことであれば、ご相談の上、寺院施設を無料でご利用いただいています。昨今では、宿泊体験、合宿、団体の研修会、グループの会合などがありました。境内は無線LAN(Wi-Fi)の環境があり、プロジェクター、スクリーン、黒板、ホワイトボード、ピアノなどを備えています。ご相談ください。
ご法話の出張いたします
住職の溝邊伸は、ご要望により法話や講演に出向きます。寺院に限らず、老人ホーム、老人クラブ、企業の研修などで、ご希望のテーマに応じてお話いたします。ワークショップ形式の研修も行います。